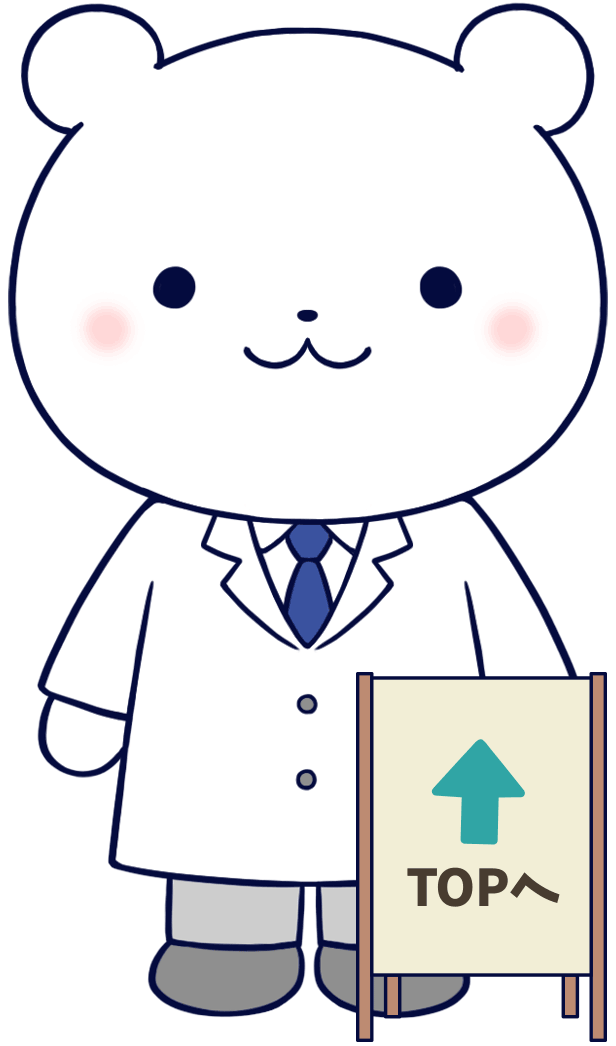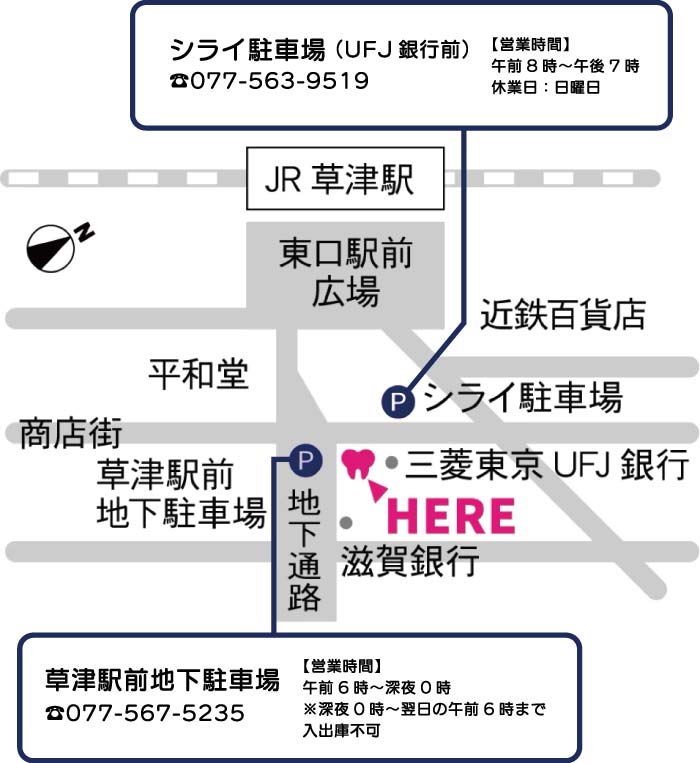受 け 口 ( 下 顎 前 突 )
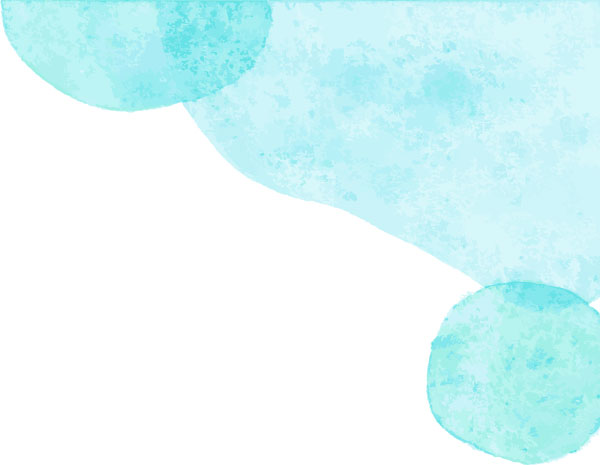

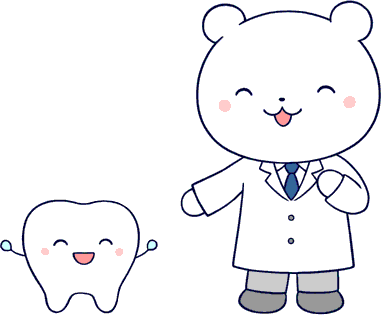
下顎前突の原因
一般に、骨格に問題がある場合には治療が大がかりになります。
骨格が原因の場合
- 上顎が小さい
- 上顎が後方にズレている
- 下顎が大きく前に出ている
歯列が原因の場合
- 上の前歯が後方(お口の内側)に傾いている
- 下の前歯が前方(唇の方向)に傾いている
生活習慣や癖などの場合
- 舌で歯を押す癖
- 5歳以降の指しゃぶり
- 爪噛み
- 口呼吸 など
どのように治療するの?
歯並び・咬み合わせに対する治療

骨格の問題に対する治療

舌の癖に対する治療

お子さま(1期治療)の場合
成長段階であることを利用し、顎の骨の成長を正しく誘導したり、顎の骨を広げることもあります。
治療しないことによる影響
前歯の外傷リスクが高い
口が閉じにくくなる
顎関節への負担
発音への影響
顔貌への影響
自信や対人関係への影響
下顎前突(受け口)についてのQ&A
子供の受け口は早くからの治療が必要とききました。何歳くらいに相談すればいいですか?
小児矯正は、一般的に小学校1~2年生頃から開始します。ただ、受け口に関しては骨格(下顎が大きい)が問題になっていることが多いため、乳歯列の時期でも構いませんので、小学校入学前頃に一度ご相談いただければと思います。
受け口は、上顎の成長が終わりに近づくほど、治療が難しくなりすので、早期に対応することで、お子様のご負担も少なくなります。
子供の受け口が自然に治ることはありますか?
乳歯が生えそろう前の1~2歳くらいでは受け口であってもおよそ半数程が自然に治るといわれていますが、3歳時点で受け口(反対咬合)であった場合は、前歯の生え変わりで正常に戻った症例はわずか5%程と言われています。
保護者様の中には、「自然治癒するかもしれない」という期待もあるかもしれませんが、早めに矯正相談を受けられることをおすすめします。
他の歯並びの乱れを含め、お子様の場合は顎の成長や永久歯への生え替わりによって歯並びが自然に治るということはあります。
ですが、保護者様の判断で「もう自然には治りそうにないから、そろそろ一度受診してみよう」というタイミングでの受診では、治療開始のベストタイミングを逸してしまう可能性があるため、必ず定期的に歯科医院を受診されることをおすすめしています。
受け口は遺伝するのでしょうか?
骨格や歯の大きさ等は、一定程度の遺伝性があると言われています。 環境要因の影響もありますが、ご両親またはどちらかが受け口である場合には、お子様が反対咬みになっていないかを注意しておき、気になったときにはすぐに受診されることをおすすめします。
受け口を治すことには、どのようなメリットがありますか?
受け口は、歯並びだけでなく顔貌への影響も大きいタイプの歯並びです。
治療により、そういったコンプレックスを解消したり少なくすることができます。
また、他の歯並びの乱れにも言えることですが、矯正治療で歯並びを整え、清掃性の高い歯並びを早くに手に入れるほど、将来的なむし歯や歯周病のリスクが抑えられ、お口の健康寿命を延ばすことが期待できます。
噛み合わせの改善によって、正しく咀嚼することができますので、胃腸への負担が軽減等の効果も期待できます。
咬み合わせの不調和
前歯の外傷リスクが高い
- 上の前歯が下の前歯より後ろに噛むため、食べ物をしっかり噛み切りにくい
- 奥歯にも不自然な負担がかかり、歯の摩耗や破折リスクが増える
顎関節への負担
- 下顎が前に出た位置で咬み合わせるため、顎関節症の原因になる
- 痛み、開口障害、カクカク音などの症状が出ることも
発音への影響
- サ行、タ行、シャ行などの発音が不明瞭になることがある
- 特に子どもでは学校生活や対人コミュニケーションでの自信に影響