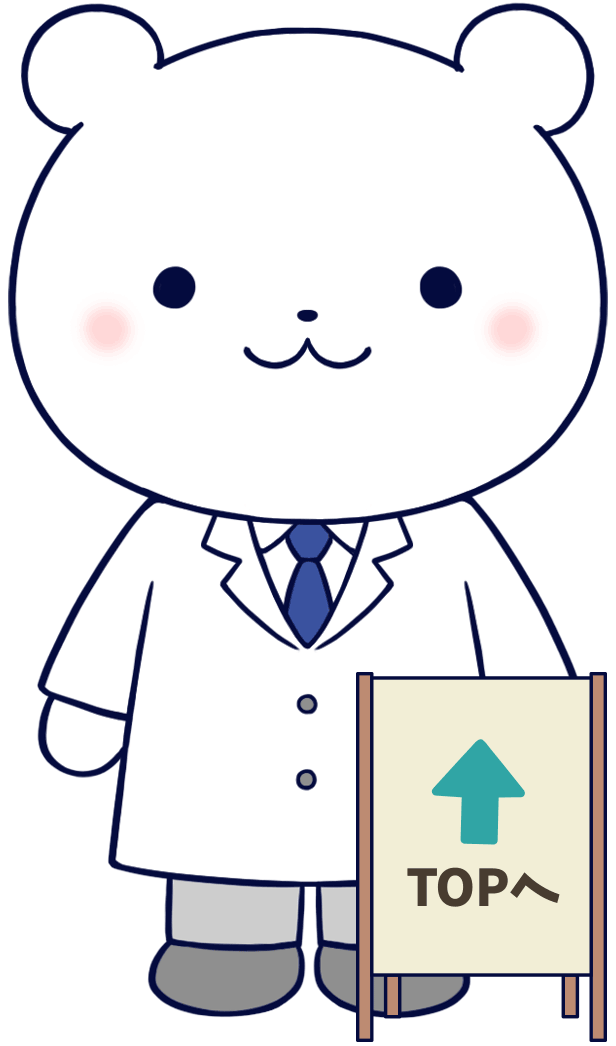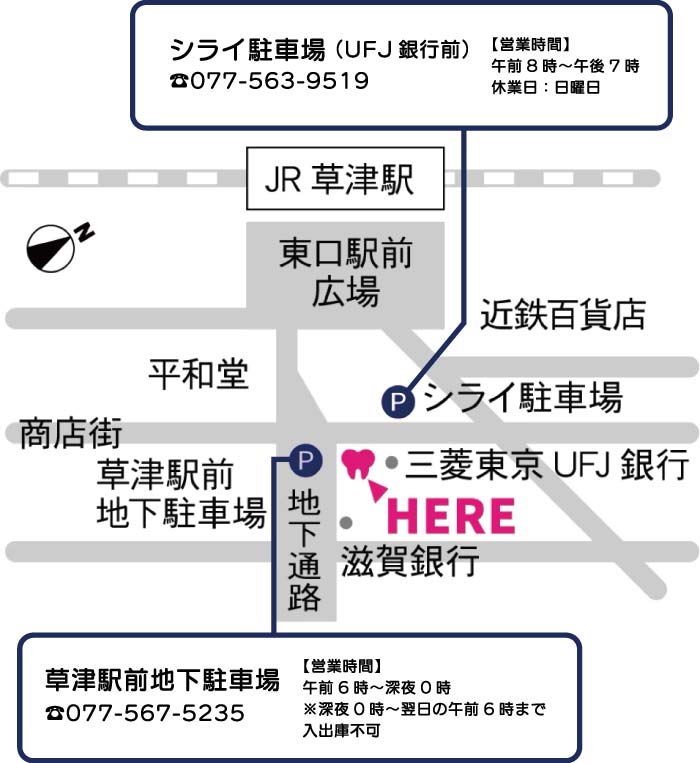開 咬
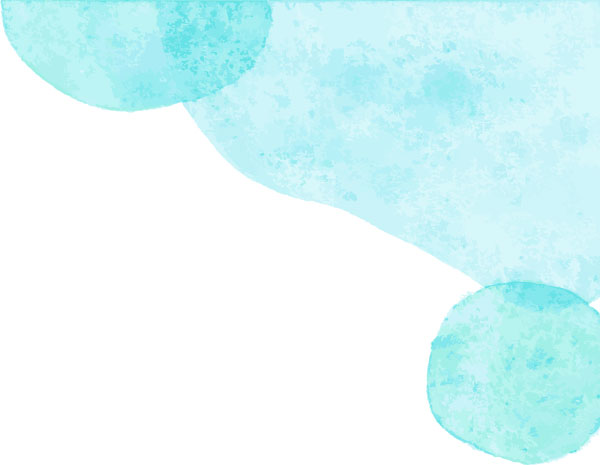

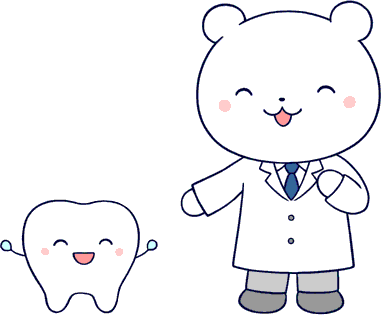
前歯が閉じれない
奥歯を噛み合わせたときに、上の前歯と下の前歯の間に、垂直方向の空間(隙間)がある咬み合わせを歯科では、「開咬(かいこう)」と言います。わかりやすく言うと、奥歯が噛み合っているのに、前歯が閉じない状態です。開咬はお口のみならず、顎関節や胃腸などにも悪影響を及ぼすことがあると言われています。
開咬の原因
開咬の原因は大きく、「骨格」「歯列」「生活習慣や癖」に分類されます。
一般に、骨格に問題がある場合には治療が大がかりになります。
骨格が原因の場合
(遺伝的要因もあります)
- 上顎骨の大きさのアンバランス
- 下顎が本来の位置より後下方に位置している など下顎が本来の位置より後下方に位置している など
歯列が原因の場合
- 上の前歯が前方(唇の方向)に傾いている
- 下の前歯が前方(唇の方向)に傾いている
- 口腔内に出ている前歯の長さが短い(歯冠部が短い)
生活習慣や癖などの場合
- 哺乳瓶やおしゃぶりの長期使用
- 舌で歯を押す癖(舌突出癖)
- 5歳以降の指しゃぶり
- 口呼吸
- 頬杖などによる偏った圧力
- 変形性顎関節症 等
どのように治療するの?
歯並び・咬み合わせに対する治療
開咬の原因が、骨格の問題ではなく、前歯の角度などに起因する場合は、ワイヤー矯正によって歯の傾斜角度をコントロールしたり、歯科矯正用アンカースクリューの使用して奥歯を歯ぐき側に沈める力をかけたり、上下の歯にゴムをかけていただくことで前歯の咬み合わせを改善すること等、患者様の咬み合わせの状態に合わせて治療を行います。
上下の前歯を咬み合わせるための治療を行います。例えば、上下の前歯にゴムをかけていただいたり、ワイヤー(針金)や歯科矯正用アンカースクリューを使用することで、奥歯を歯ぐき側に沈める力をかけるなど、患者様の咬み合わせの状態に合わせて治療を行います。

骨格の問題に対する治療
上顎骨のアンバランスや下顎が本来の位置より後下方に位置している等、顎の大きさや位置に問題がある場合には、矯正治療だけでは改善できない場合があります。そのような場合には、外科手術で上顎骨や下顎骨を部分的に切り取ったり、顎の位置を動かしたりすることになります。

舌の癖に対する治療
舌癖(上下の隙間に舌を入れてしまう、舌で歯を押してしまう等)を原因とする場合、骨格的には問題がないこともあります。矯正装置により上下の前歯の角度を改善しながら、舌癖改善のためのトレーニング(筋機能療法)を行います。矯正治療と併行して舌のトレーニングを行うことで、矯正治療がスムーズに進んだり、矯正治療後の後戻りを少なくすることができます。

外科的な処置
短い舌小帯(舌の裏のひだが短い)やアデノイド肥大、扁桃腺肥大がある場合、外科的な処置を行うことで治療することもあります。外科処置の必要性は、状態や年齢によって異なります。

お子さま(1期治療)の場合
永久歯の前歯が生え揃う時期(小学校1~2年生頃)であれば、比較的少ない負担で矯正治療を行えます。
まずは、原因(吸指癖や舌癖)の除去が最も有効です。
舌の癖を改善したり、咬む力をトレーニングするためにMFT(口腔筋機能療法)を行ったり、舌が前歯に当たらないようにするための装置(タングクリブなど)を装着することもあります。子供の時期からこのように癖の改善を行うことは、適応能力も高く、成長もコントロールしやすいことから、より効果的であると言われています。
また、成長段階であることを利用し、顎の骨の成長を正しく誘導したりすることもあります。
歯並びが気になりましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
治療しないことによる影響
口が閉じにくくなる
唇が閉じにくいことで、口呼吸になりやすいです。口呼吸が続くと、口臭やむし歯、歯周病のリスクが高まる他、免疫力の低下や集中力が低下したり、身体の代謝も落ちてしまうことがあるといわれています。
顎関節への負担
下顎が前に出た位置で咬み合わせるため、顎関節症の原因になることもあります。痛みや開け口障害、カクカク音などの症状が出ることもあります。
早期の奥歯の喪失
開咬の場合、咬み合っている奥歯ばかりを使うことになるため、奥歯に過度な負担がかかってしまいます。そのため、奥歯が長持ちしづらいことがあります。
発音への影響
サ行やタ行、ラ行等の発音が不明瞭になることがあります。特にお子様の場合は学校生活や対人コミュニケーションでの自信に影響することもあります。
顔貌への影響
口を閉じたときに上下の前歯が接触しないため、歯の隙間が目立ち、特に笑ったときや話すときに前歯のすき間が強調されることがあり、笑顔にコンプレックスを感じやすいともいわれています。骨格性の開咬では、下顔面(鼻の下~あごの先まで)が長い傾向にあるため審美的なコンプレックスを感じる方もいらっしゃいます。
自信や対人関係への影響
お子さまの場合、成長に伴って開咬の程度がより顕著になる可能性もあります。
※きれいな歯並びや整った口もとは、成長過程の子ども達にとって、自尊心の向上やコミュニケーションを行う上で有益であることが明らかにとなっています。
開咬についてのQ&A
開咬と言われましたが、現状で特に困っていることはなくても、治した方が良いですか?
歯並びの乱れに伴うリスクは、ご自身で自覚することは難しいかもしれません。例えばですが、麺類やレタスなどを前歯で噛み切るのが難しい(噛み切ることができない)ということはありませんか?このような場合は、よく噛まずに飲み込むことで胃腸に負担をかけている可能性があります。また、咬み合っている奥歯ばかりを使うことになるため、奥歯に過度な負担がかかってしまいます。
唇が閉じにくいことで、口呼吸になりやすく、口呼吸が続くと、口臭やむし歯、歯周病のリスクが高まる他、免疫力の低下や集中力が低下したり、身体の代謝も落ちてしまうことがあるといわれていますので、できる限り、治療を受けることをおすすめしています。
開咬は奥歯を早くに失う原因になるとききました。なぜなのでしょうか?
開咬では、上下の前歯で噛むことが難しいため、必然的に奥歯の負担が大きくなります。偏った力がかかることで、歯・歯茎・顎の骨にダメージが蓄積され、奥歯を早くに失ってしまう可能性が高くなります。
気になる場合は、早めにご相談ください。
子供が指しゃぶりをやめられません。開咬の原因になることがあるときいて、心配しています。
指しゃぶりが歯並びに影響しやすくなるのは、5歳ごろ(歯の生え変わりが始まる頃)を過ぎても続く場合だといわれています。それまでは、指しゃぶりは心を落ち着かせるための行動でもあるため、無理にやめさせなくても大丈夫です。
5歳以降も続くときは、叱るよりも、
・指しゃぶりをしていないときにほめる(小さな成功体験を積む)
・積み木・粘土・折り紙など手を使う遊びを取り入れる(手が忙しいと自然と指しゃぶりが減ります)
・寝る前は添い寝や読み聞かせでリラックスさせる
といった環境づくりや代わりの行動が効果的です。また、歯並びの乱れは指しゃぶり以外の原因でも起こります。歯並びが気になる場合は、お気軽にご相談ください。
どのように治療するの?
どのように治療するの?
歯並び・咬み合わせに対する治療

舌の癖に対する治療

外科的な処置

治療しないとどうなるの?
奥歯に負担がかかり、顎関節症になりやすい
発音問題
消化不良に繋がる